心がふっと軽くなる 「はじめての介護の心得」
介護は突然はじまることも多く、最初は不安だらけだと思います。
いつまで続くのか見通しも立たず、自分だけで介護をしようとすると、一生懸命になりすぎて、気が付いたときには、お互いにきつい介護になってしまうことも。
だからこそ、はじめから「頑張らない」と決めること。
それは、“介護をしない”ことではなく、一人で、家族だけで、“背負わない”ということ。
自分のまわりの使える制度(介護保険など)や頼れる人たちをしっかりと把握して、使えるものは使って、心身の負担を軽くすることが大切です。
はじめての介護の心得
3つのキーワード
その1. 暮らしを新しく設計する
介護を必要とする人の状況は変わってきます。
まずは家の中のこと、家族のこと、自分のことを俯瞰し、誰もが自分らしく毎日を過ごせる暮らしを新しく組み立てましょう。
●介護の分担を決める

介護が必要となった時点で、家族や親せき・離れて暮らす兄弟姉妹とも相談しましょう。
一人で背負うことがないよう経済的なこと、介護自体もできれば分担し、みんなで見ていくことが大切です。
●動きやすい環境を整える
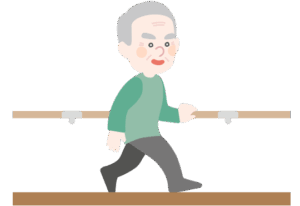
車いすや杖で移動することを考え、段差や階段など家中の「足元」を見直し、ケガすることのないよう安全な環境を整えましょう。
●介護から離れる時間をつくる
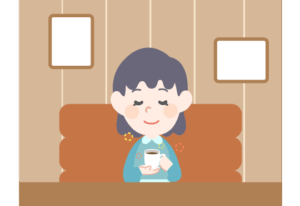
できる限りこれまでの自分の生活を変えないこと。仕事を続ける、趣味に没頭できる時間をつくることを心掛けましょう。
その2. 本人の気持ちを尊重する
「できることは自分でやりたい」。介護を必要とする本人の気持ちを尊重し、できることを増やしてあげましょう。本人にとっても、介護する人にとっても、じつは負担が減ることにつながるのです。
その3. 頼れるものは積極的に活用する
介護で受けられる公的なサポートは、お住まいの地域包括支援センター、もしくは役所の高齢福祉課などで相談を。また、介護用品など便利なアイテムは、介護保険を活用して積極的に利用しましょう。

この記事の監修
浜田きよ子 先生
この記事の監修
浜田きよ子 先生
- 高齢生活研究所 所長
- 排泄用具の情報館「むつき庵」代表
- NPO排尿ネットの会 理事



